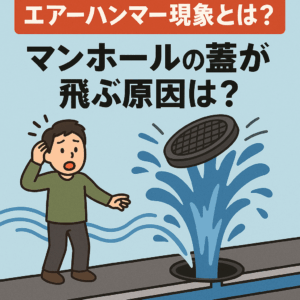
下水道のマンホールが突然「ボンッ!」と音を立てて飛び上がる――そんなニュースを耳にしたことはありませんか?
これは単なる事故ではなく、多くの場合「エアハンマー現象」と呼ばれる現象が関係しています。
この記事では、エアハンマー現象の仕組みや発生条件、対策方法までわかりやすく解説します。
もくじ
エアーハンマー現象とは?地下で何が起きている?
エアハンマー現象とは、下水道や配管の中で空気のかたまりが急に押し縮められたり、逆に一気にふくらんだりすることで、大きな衝撃が発生する現象です。あたかも巨大なハンマーが管内を叩くような衝撃波が生じることから、「エアーハンマー(空気槌)」という名が冠されました。
イメージとしては、自転車の空気入れを勢いよく押し込むと「シュッ」と強い圧力が出るのに似ています。空気が閉じ込められた状態で一気に押されると、その力は非常に大きく、周囲に強い衝撃を与えます。
下水道の場合、大雨やポンプの動きなどで空気が管の中に入り込み、その空気が水の流れに押されて急に動いたり圧縮されたりします。このときに発生する圧力の変化が、時にはマンホールの蓋や周囲の舗装を持ち上げるほど強い力になることがあります。
エアーハンマーの流れとしては、
-
大雨などで下水管に大量の水が流入
-
水に押し出された空気が閉じ込められる
-
空気が急激に圧縮・移動
-
突然の開放で「ドン!」と衝撃波や強い水柱が発生
その結果として、マンホールの蓋が飛ぶ・破裂音が鳴る・道路が陥没するなどの危険が起こることがあります。
マンホール蓋が飛ぶ仕組み
下水道では、雨水や汚水が流れる際にポンプや落差、流れの変化などで空気が巻き込まれ、空気溜まりができます。
急な流れの変化でこの空気が圧縮されると、衝撃波が前後に伝わり、特にマンホールのような開口部付近で瞬間的に高い圧力がかかります。
最近の事例では、圧力開放型マンホール(格子状の蓋)でも圧力が周囲舗装に及び、舗装ごと持ち上がるケースが確認されています。蓋が重いから安全とは限らず、構造物全体での対策が必要です。
発生しやすい条件
エアハンマー現象は、以下の条件が重なったときに起きやすくなります。
-
急速充填(集中豪雨など)で通気・排気が追いつかない
-
高所に空気溜まり(サミット)ができ、移動・圧縮される
-
ポンプや弁の急停止・急起動による流れの急変
-
構造上、空気が抜けにくい管路設計
これらの条件は、豪雨時やポンプ運転時に重なると危険度が高まります。

こちらは、ゲリラ豪雨によって引き起こされた実際の“エアーハンマー現象”を取材したニュース映像です。神奈川県横浜市でマンホールの蓋が飛び、床上浸水が発生する様子がリアルに映されています。
エアーハンマー現象の防止対策は?
エアーハンマー現象を防ぐには、設計から運用まで様々な対策を講じる必要があります。
-
空気抜き弁や通気管の設置
空気溜まりを排除し、圧縮される前に外へ逃がす。 -
流れの制御
管の勾配や落差を適切に設定し、急激な流速変化を避ける。 -
運転条件の工夫
ポンプや弁の操作を急激に行わず、ソフトスタート・スローストップを採用。 -
貯留・越流施設の活用
流入ピークを抑え、急速充填を避ける。 -
マンホール飛散防止
ロック機構やヒンジ付き、圧力開放型を採用し、周囲構造も補強。 -
定期的な点検・清掃
堆積物を除去し、流れの阻害や空気溜まりを防ぐ。
私たちはどう気をつければいいのか
既存のインフラ全て対策がとられ完全に改修することは難しいため、私たち一人ひとりの注意も非常に重要です。
エアハンマー現象は、通常ほとんど発生しません。しかし、台風や集中豪雨のときには発生のリスクが高まります。私一人ひとりの注意が必要です。
-
大雨時にマンホールや側溝の近くに立ち寄らない
豪雨のときは、見た目に異常がなくても内部で圧力が高まっている可能性があります。マンホールや側溝の上・周囲は避けて通りましょう。 -
道路冠水や水が渦を巻いている場所には近づかない
強い流れや渦は空気や水圧の変化を伴う場合があり、足を取られる危険もあります。 -
車で冠水道路を通らない
流れに押し流される危険だけでなく、下水道のフタが外れていて落下する事故もあります。 -
災害情報を事前にチェックする
気象庁や自治体の防災情報アプリで、大雨警報や避難情報を早めに確認しましょう。 -
子どもに教えておく
大雨のときに水たまりで遊ばないこと、マンホールや側溝は危ないことを事前に伝えておくと安心です。 - 異常を発見したらすぐに連絡
もし、マンホールの蓋がずれていたり、水が噴き出していたり、異常な音が聞こえたりした場合は、危険ですので絶対に近づかず、速やかに各地方自治体の道路管理者や下水道部局に連絡してください。
まとめ
エアハンマー現象は、下水道や配管内で空気が急激に圧縮・解放されることで発生する衝撃現象です。
普段は見えない管の中で瞬間的に大きな力が発生し、条件によってはマンホールや舗装が持ち上がることもあります。
安全を確保するには、空気抜きや流れの制御などの構造的対策と、運転管理・点検の両面からの取り組みが不可欠です。
この現象を知ることは、都市の防災やインフラの安全性を考えるうえで重要な一歩になります。

東京・新宿駅前で発生した事例を解説動画形式で紹介。「なぜ飛ぶのか」に焦点を当てています。
補足:ウォーターハンマーとの違いとは?
エアーハンマー現象とよく似た言葉に「ウォーターハンマー(水撃作用)」があります。ウォーターハンマー(水撃作用)とは、配管の中を流れている水が急に止まったり、流れの向きが急に変わったときに発生する衝撃現象です。
蛇口をパッと閉めたときに「ガンッ」と音がするのはこの現象の一例で、水の勢いが管の内壁にぶつかり、大きな力や音を生じます。
| 項目 | エアハンマー現象 | ウォーターハンマー(水撃作用) |
|---|---|---|
| 主な原因 | 管の中にたまった空気が急に押し込まれたり押し出されたりする | 管の中を流れる水が急に止まったり流れが変わる |
| 発生のきっかけ | 大雨やポンプの急作動で空気が圧縮・解放される | 蛇口やバルブを急に閉める、ポンプを急停止する |
| 衝撃の伝わり方 | 空気が膨張・収縮し、その圧力が水や構造物に伝わる | 水の慣性が壁にぶつかり、その衝撃が配管に伝わる |
| 身近な例え | 自転車の空気入れを勢いよく押す | 蛇口を急に閉めたときの「ガンッ」という音 |
| 被害例 | マンホールの蓋や舗装が持ち上がる | 配管の破損や接続部からの水漏れ |
